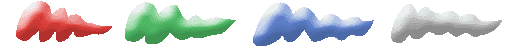
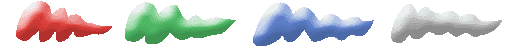
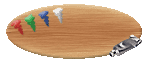





|
|

|
歯の神経抜かず痛み除去 愛院大などが再生治療法 愛知学院大歯学部(名古屋市)の中村洋教授らのグループが、国立長寿医療センター(愛知県大府市)の中島美砂子室長と共同で、傷んだ歯髄(歯神経)を抜かずに元通りにする新たな治療法を開発した。これまでは、歯髄を取り除くしか治療法がなかった。 中村教授らによると、患部に「MMP3」という酵素を適量塗り込むと、血管が再生して歯髄がよみがえる。ラットを使った動物実験では、1−2日で再生が始まった。虫歯そのものは治らないが、虫歯が歯の中心にまで達し、熱い物や冷たい物がしみる「歯髄炎」に効果がある。中村教授らは、傷ついた歯髄内にMMP3が多く分泌されていることを発見。「再生能力があるのでは」と予測し、治療への応用を考えついた。 ひどい虫歯では、歯髄を取り除く治療が多く行われているが、歯の感覚がなくなるため再び虫歯になっても気づかず抜歯に至る可能性が大きかった。 こうした抜歯を減らすことで、医療費の抑制につながる可能性もあるという。研究チームは2007年から動物実験に着手。研究は、内閣府から先端医療開発特区(スーパー特区)に選ばれており、人体に対する安全確認など課題をクリアした上で、実用化を目指している。歯髄に詳しい東京医科歯科大大学院の須田英明教授(歯髄生物学)は「生涯を自分の歯で過ごせる可能性を高める発見。画期的だ」と評価している。 【中日新聞】 |
20年11月7日
歯科治療で血管炎治癒 小児期からのケアを
小児の血管炎の一種で、再発や腎炎への進行が問題になる「ヘノッホ・シェーンライン紫斑病」の多くのケースが、虫歯や根尖性歯周炎など歯科の病気や、副鼻腔炎など耳鼻科の病気の治療によって治るとする研究結果がまとまった。
背景には、細菌やウイルスによる炎症が離れたところに影響を及ぼす「病巣感染」があるといい、病気を慢性化させないケアが小さいうちから重要なことを示している。
研究の中心となった仙台赤十字病院の永野千代子小児科部長によると、ヘノッホ・シェーンライン紫斑病はアレルギーが絡んだ原因不明の病気とされ、5〜6歳が発症のピーク。患者には隆起した出血斑がみられるほか、関節の痛みや腹痛、腎炎を合併する場合もある。日本を含むアジアで頻度が高いという。
永野さんが病巣感染との関連に興味を持ったきっかけは、1999年に担当した当時11歳の男児。「血尿などがあり感染性の腎炎を疑ったが、虫歯だらけで口内の衛生状態が非常に悪いことに気付き、歯科に診察を依頼した」という。
永久歯のうち13本が、歯髄にまで虫歯が及んで起きる根尖性歯周炎だと分かり、抗生物質による腎炎の治療と並行して虫歯を治療した結果、血尿などは治まった。ところが、14歳の時に再び虫歯ができると、男児は血尿やタンパク尿も再発した。
そこで永野さんらは99年以降、ヘノッホ・シェーンライン紫斑病と診断した40人について、歯科や耳鼻科と協力して背景に潜む病巣を検討した。
70%に当たる28人には虫歯や根尖性歯周炎があり、うち16人は副鼻腔炎や中耳炎、扁桃炎なども合併していた。一方、歯の病気はなかったものの副鼻腔炎だったのは5人で、うち1人は扁桃炎を合併していた。
「虫歯や副鼻腔炎で細菌などの抗原に慢性的にさらされると、病巣感染の主体と考えられる扁桃に障害が起き、免疫機能に異常が生じる。ヘノッホ・シェーンライン紫斑病などはこうして発病したのでは」と永野さん。
治療は抗生物質を基本に、腹痛や関節痛のある患者にはステロイド剤も投与。根尖性歯周炎は、乳歯の場合は抜歯することが多いが、永久歯に影響が及びそうな場合などは抜かずに治療した。このほか、患者全員と家族で口の中の洗浄や歯磨き、食事指導も実施した。
【IDN】
20年7月1日
歯周病の治療で血管機能が改善
この研究は、英イーストマン歯科病院(ロンドン)で重症の歯周病(歯を支える歯肉および骨の慢性的な細菌感染)をもつ患者120人を対象に実施したもの。歯周病の集中的治療を行った群では、治療直後に炎症の増悪がみられたものの、6カ月後には血管の内側を覆う内皮の機能改善が認められた。また血管が拡張して血流が改善したほか、内皮細胞の健康状態を示す分子マーカーでも改善が示された。例えば、6カ月後の集中治療群の動脈内腔が通常治療群よりも2%拡張しており、改善の程度と歯周病治療との間に相関があることも明らかにされた。
米国歯周病学会(AAP)のPreston D. Miller博士は、この研究は局所炎症と冠動脈の炎症との関連をさらに強く裏付け、歯周病と心血管リスクに関する情報蓄積に大きな前進をもたらすものだと支持。ただし、特定の歯周病治療による効果を明らかにするには、さらに研究が必要だという。
一方、米国歯科医師会(ADA)のDaniel Meyer博士は、今回の研究をはじめ、歯周病と心血管疾患との関係を示す一連の研究では、各危険因子の相対的な重要度が示されておらず、食事、運動、全身の健康などの関与が考慮されていないため、疾患の1つの側面しか見ていないという。心臓発作、脳卒中などの心血管疾患に対し歯周病がどれほどの影響をもつかはまだわかっておらず、喫煙、飲酒をする人や肥満の人は口腔内の健康に気をつける必要があるが、そのほかの因子にも同様に注意するべきだと同氏は述べている。
米コロンビア大学(ニューヨーク)Mailman公衆衛生学部准教授Moise Desvarieux博士は、この研究が歯周炎と血管疾患との関連を示す証拠を補強するものであり、また、歯周病を治療することで血管内皮機能が改善していることから、可逆性をもつ可能性もあると指摘している。
糖尿病協会理事長 糖尿病治療は歯科との連携必要
日本糖尿病協会の清野裕理事長は先月2日、日本歯科医師会主催のシンポジウムで講演し、歯周病の治療が糖尿病の治療に果たす役割は大きいとして、「糖尿病治療に医科と歯科が連携して取り組むことが求められている」と述べた。その上で、医科・歯科連携の具体策として、近く日本医師会と日本糖尿病学会、日本糖尿病協会で構成する「日本糖尿病対策推進会議」に日歯が参加することになると発表した。
清野理事長は、「動脈硬化を促進させる因子として歯周病がクローズアップされている」と話し、具体例として歯周病専門の歯科医師に協力してもらい、糖尿病患者に歯周病の治療を行った事例を紹介。治療の結果、歯石除去とブラッシングでヘモグロビンA1Cが0.4%低下し、さらに抗生物質も使うと、0.7%下がったという。「0.7%は血糖降下薬に匹敵する結果で、医科歯科の連携の重要性が分かった」と報告した。

五箇村
3月17日
北海道歯、残存歯数の医療費への影響を発表
残存歯数が少なくなるほど平均医科診療費が高くなるとの調査結果を北海道歯科医師会(富野晃会長)が発表した。北海道の依頼を受けた道国民健康保険連合会が実施まとめたもので、今回発表されたのは「8020運動に基づく歯と全身の健康に関する実態調査」の概要版。
調査は昨年5月に道内の国保被保険者(旭川市を除く)の70歳以上(老人保健を含む)で、歯計医療機関を含む医療機関の受診者を対象にした。
分析に用いたレセプト件数は医科が10万3418件、歯科は6万4132件。1カ月当たりの医科診療費と現在歯数、欠損補綴状況、歯周病などとの関連を調べた。
20歯以上、15〜19歯、10〜14歯、5〜9歯、0〜4歯の5段階での残存歯数と平均医科診療費の関係では、20歯以上群2万2660円に対し、0〜4歯群は3万5930円と約1.6倍高くなっている。
70〜74歳、75〜79歳、80歳以上の5歳ごとにおいても全体と同様の結果が見られる。
欠損補綴状況と平均医科診療費の関係では、「補綴済み」群は2万7120円、「要補綴」群3万290円に対し「補綴必要なし」群は2万6410円と有意に低くなっている。
また、歯周病との関係では、「異常なし/歯肉炎」群2万4170円に対し、「重度」群は2万7920円と3千円以上高くなっている。
生活習慣病における平均医科診療費と残存歯数の関係では、20歯以上の2万7730円に対し、0〜4歯群は4万2460円と約1.5倍高くなっている。
2月1日
「虫歯」を防ぐチョコの意外な効果
―虫歯菌の作用を抑え、歯垢もできにくくする―
2月14日のバレンタインデーを控え、コンビニエンスストアやデパートで、バレンタイン商戦が本格化してきた。バレンタインデーといえば、やはり「チョコレート」。最近は、お菓子としてだけでなく、カカオに含まれるさまざまな成分の健康効果にも注目が集まっている。
例えば、チョコレートに含まれるポリフェノールやカフェインなどには“ダイエット効果”があるとされており、ギャバ(GABA;γ-アミノ酪酸)には、不眠やイライラを改善する効果があると言われている。
一方で、チョコレートは食べ過ぎると虫歯になりやすいというイメージを持っている人も少なくないだろう。ところが最近の研究報告によると、チョコレートには逆に虫歯を予防する効果があることが分かったというから驚きだ。
カカオパウダー摂取で虫歯スコアが減少
これは、明治製菓と日本大学松戸歯学部の福島和雄氏らの研究グループによる実験で明らかになったもの。まず、36匹のラットを4群に分け、3群は虫歯の原因菌の一つ、レンサ球菌に感染させた。
レンサ球菌に感染させていない群には普通の食事を与えた。レンサ球菌に感染させた3群はさらに、(1)普通の食事群、(2)ホワイトチョコレートの主成分、カカオバターを24%加える群、(3)同量のカカオバターと0.5%量のカカオパウダーを加える群――に分けた。全群の食事には、ショ糖が35%含まれるようにした。
56日後に、各群の虫歯スコアを調べた。その結果、レンサ球菌に感染させていない群は7.4、感染させた群では、(1)普通の食事群32.9、(2)カカオバター群17.2、(3)カカオバター+カカオパウダー群10.8だった。カカオバター群およびカカオバター+カカオパウダー群は、普通の食事群に比べ、虫歯スコアを約半分に低くする効果があったわけだ。
ところで、カカオバターとカカオパウダーはどう違うのだろうか。炒ったカカオ豆をすりつぶし、どろっとしたペースト状にしたものがカカオマス。カカオマスは、白っぽい淡黄色で、口溶けのよい油脂分のカカオバターと、苦みのある褐色のカカオパウダーに分けられる。
普通の褐色のチョコレートは、カカオマスにカカオバターと砂糖などを混ぜて作られる。カカオバターのみに、粉乳と砂糖などを加えるとホワイトチョコレートになる。
カカオにはピロリ菌や大腸菌などの抗菌作用
では、カカオバターやカカオパウダーを加えると、なぜ虫歯スコアが低くなるのだろうか。以前から、カカオには、ピロリ菌や大腸菌などに対する抗菌作用があることが知られている。
そこで、福島氏らは、培養細胞を用いた詳しい実験を行い、カカオパウダーが虫歯の原因菌のグルコシルトランスフェラーゼという酵素の働きを阻害することを見出した。グルコシルトランスフェラーゼは、歯の周りの糖分を、水に溶けないグルカンという形に変える作用がある。
歯に付着しているグルカンに菌がたくさん住み着くと、歯垢(プラーク)となり、やがて虫歯や歯周病を起こすと考えられている。カカオパウダーには、抗菌作用にとどまらず、歯垢をできにくくする働きもあることが明らかになった。
もちろん、チョコレートに虫歯を防ぐ働きがあると言っても、虫歯や歯周病予防のために、日ごろからの歯のケアが大切なのは言うまでもない。
【nikkeibp健康】活性酸素減らす物質発見
がん、動脈硬化の治療法開発に光 熊本大
がんや動脈硬化、老化などの原因と言われる活性酸素を減らす物質が体内で作られるメカニズムを、熊本大学大学院医学薬学研究部の赤池孝章教授らのグループが明らかにした。研究が進めば、がんの予防・治療などへの応用につながりそうだ。英科学誌「ネイチャー・ケミカルバイオロジー」11月号に紹介された。
赤池教授らは、体内で作られ、血管拡張などの働きを持つ「環状グアノシン1リン酸(cGMP)」という物質が、一酸化窒素と結び付くと、ニトロ化環状グアノシン1リン酸(8−ニトロcGMP)という新しい物質になることを発見。この物質も血管拡張の働きを持つが、その効果はcGMPの約100倍に達した。さらに8−ニトロcGMPが細胞内のある種のたんぱく質と結びつくと、活性酸素を減らす酵素をたくさん作り出すことも明らかにした。活性酸素は、たばこやアルコール、油の取り過ぎなどで多く発生するといわれ、動脈硬化やがんなどの原因の一つとされている。
98年にはcGMPの働きなどを明らかにした米国の研究者ら3人がノーベル医学・生理学賞を受賞しているが、8−ニトロcGMPの存在や、その働きまではわかっていなかった。
東北大学大学院医学系研究科の下川宏明教授(循環器病態学)は赤池教授らの研究について「がんや動脈硬化などの治療法の開発に結びつく可能性があり、非常に素晴らしい研究だ」と話している。
「八〇二〇」に寄せて
間野 あき 98歳(歯数 26本)
木村 義匡 81歳(歯数 29本)
私の体験
池谷 秀夫 88歳(歯数 29本)
健康で快適な生活を送る為には、胃腸の状態が大切だと思います。
食物をよく噛んで胃や腸に送るには、丈夫で良い歯が必要です。私は日頃次の様に歯の管理につとめて参りました。
食後の歯磨きを励行し、必要により歯間ブラシの使用、又デンタルミラーで口の中を観察して、異状を認めた時は早期の治療につとめています。なお定期的な医師の検診を受けて、歯周病の予防につとめています。なお医師から作って戴いた「スプリント」を寝る前につけて、歯の損傷を防止しています。お陰で八十八歳の今日まで、歯の痛みを感じた事はありません。
親から授かった歯を大切にして、自分の歯で美味しく食事を戴き、明るく元気に生活の出来ることを願っています。
勝又 和作 81歳(歯数 30本)
けがや事故で歯が抜けたり欠けたりした場合に備えてもらおうと、神崎郡歯科医師会は九日、郡内の小、中学校、高校の全二十六校に、抜けた歯を漬けることで再植治療成功の可能性を高める保存液を配った。これまで、個別で保存液を備えてきた事例はあるが、歯科医師会単位で全校に導入したのは全国でも珍しく、県内では初めて。
歯の根元にある「歯根膜」という組織は乾燥に弱く、口の外での生存は三十分ほど。そのため、抜け落ちた歯を長時間外に出した後で歯医者に持参しても、元通りに植え付けるのは困難という。保存液は、歯根膜の細胞を維持できるよう、浸透圧やpHを調節してある。
一本約千五百円と安価だが、液の普及や理解が進んでいないことを疑問に感じた同会が、「子どもたちの歯を守りたい」と、全校に備えてもらうことにした。
同会は各校の養護教諭らと合同研修会を開催。保存液の役割や、けがや事故の際の応急処置方法について説明し、液を全校に配った。
学校歯科担当理事の原田博紀さんは「神崎郡での取り組みを機に各地でも広まってほしい」と話している。
【神戸新聞】
事故などで歯が抜けてしまった場合、保存液などを使い、乾燥させないようにして、できるだけ早く歯科医院へ持参していただけると再殖することができます。
11月21日 京都の秋

11月12日
糖尿病協会理事長 糖尿病治療は歯科との連携必要
日本糖尿病協会の清野裕理事長は先月2日、日本歯科医師会主催のシンポジウムで講演し、歯周病の治療が糖尿病の治療に果たす役割は大きいとして、「糖尿病治療に医科と歯科が連携して取り組むことが求められている」と述べた。その上で、医科・歯科連携の具体策として、近く日本医師会と日本糖尿病学会、日本糖尿病協会で構成する「日本糖尿病対策推進会議」に日歯が参加することになると発表した。
清野理事長は、「動脈硬化を促進させる因子として歯周病がクローズアップされている」と話し、具体例として歯周病専門の歯科医師に協力してもらい、糖尿病患者に歯周病の治療を行った事例を紹介。治療の結果、歯石除去とブラッシングでヘモグロビンA1Cが0.4%低下し、さらに抗生物質も使うと、0.7%下がったという。「0.7%は血糖降下薬に匹敵する結果で、医科歯科の連携の重要性が分かった」と報告した。
日歯が国民向けに歯周病と糖尿病の関係の資料集を発行
日本歯科医師会(大久保満男会長)は、歯周病と糖尿病の関係を国民に分かりやすく説明するための資料集を発行した。
東京歯科大学歯周病学講座の山田了教授と同大水道橋病院の森山貴史氏から提供された医学的知見を全82枚のパワーポイントでまとめたもので、資料集とともにデータを収録した添付CD−Rを活用できる。
歯周病について、罹患率や影響、リスクが確認できるチェックリストなどの説明や、検査方法、治療の流れ、予防対策まで盛り込んでいる。
更に、全身に及ぼす影響として、血管系疾患や心内膜炎、誤嚥性肺炎、低体重児出産などとの関係にも触れている。
糖尿病との関係では、日本人に多い2型糖尿病に着目した解説や歯周病との相関作用を紹介している。
図や表、写真を多く使用し、分かりやすくまとめた。
10年11月8日
隣家の小笠原さんが丹誠込めてお作りになった菊を診療室の玄関に飾ってくれました。
来院のおりに鑑賞してみてください。


19年11月2日
おもしろGoods バグミー
バグミーってご存じ???。口の知恵の輪です。グミを口の中でいじって穴に通したりいろいろ操作します。効用は・・口を運動させることで脳の老化を防ぐものです。これにはれっきとした根拠があります。
詳しくは![]() パグミー
パグミー
19年10月30日
口腔内細菌と流産
ある種の細菌が、口腔内から胎児をつつむ羊水に移り住んでいる可能性が明らかになった。実際にこのようなことが起こると、流産の危険性が高まるほか、早産を含めた様々な併発症を起こす可能性が高くなるとする報告が出た。
通常、胎児を包む羊水は無菌状態。陰部からの感染症や羊水穿刺で生じた羊膜の感染症による早産は実際に報告されている。今回報告されたのは、特に炎症のある歯肉が存在する女性の口腔内の細菌が血流を介して羊水に至り、感染症をおこしうるとする仮説。
今回の報告では、帝王切開での出産を予定している48人の妊婦の羊水と口腔内プラークを調べた。対象者の平均年齢は31歳だった。
結果、48サンプルのうち7サンプルで口腔内に良く見られる細菌のDNAを検出。これらの細菌は培養することができず、DNA検査により存在が明らかになったものの、細菌の数や実際に感染症を起こしうるレベルであるのかに関しては不明だった。
この研究結果は英国産科婦人科誌に掲載されている。
今回の報告では、口腔内細菌、羊水に存在する細菌と過去の妊娠に関する履歴―流産や早産、羊膜の早期剥離や新生児死に関して関係があることも明らかにした。
「DNAは組織内に長くとどまるので、前回の妊娠時に存在した細菌のDNAが残っている可能性が高いことは明らかにされている」と論文は綴られている。著者は英国ロンドンにあるクイーンメリー医科歯科大学のキャロライン・ベアフィールド医師ら。
今回の所見を明らかにするには、更なる追加研究が必要だ。
論文の記載から。“今回の研究ではPCRと呼ばれる非常に感度の高い検査で細菌のDNA検出を行った。その結果、従来の感度の低い検査報告では関係が明らかにできなかった妊娠の併発症と細菌感染症の関係が初めて明らかになったと考える。”
【2002年7月13日/米・ニューヨーク】
19年10月28日
歯は健康のバロメーター 歯が少ない人ほど医療費増
兵庫県歯科医師会が、県内の70−89歳の約2万7000人を対象に、1カ月間の医療費を調べたところ、自分の歯がゼロの人は20本以上ある人に比べ、月額で約1万5000円高いことが分かった。歯の少ない人ほど糖尿病や認知症など重い疾患を抱え、医療費がかさむケースが多く、同会は「歯が健康な人ほど元気でいられるということを示している。歯の大切さをアピールするきっかけになれば」としている。県歯科医師会によると、歯の本数と幅広い疾患の医療費の関連を調べたデータは初めてという。
同会は六年前から、国民健康保険団体連合会の協力を得て、全国に先駆けて口腔(こうくう)と全身の健康の関係を調査している。八十歳まで二十本以上の歯を保つ「8020運動」の一環で、今回は二〇〇五年五月の診療報酬明細書(レセプト)のデータを分析した。
その結果、歯が二十本以上の人と比べ、ゼロの人は一万四千八百十三円、一〜九本の人は六千六百五十六円、十〜十九本は二千八百四十九円、それぞれ一カ月の医療費が高かった。
また、疾患ごとに歯が少ない人と多い人の有病率を比べたところ、糖尿病はゼロの人のうち8.2%で認められたが、二十本以上の人は7%▽認知症はゼロの人1%に対し、二十本以上は0.3%▽心臓など循環器系疾患はゼロの人5%に対し、二十本以上は3%−など、歯の少ない人の方が深刻な疾患を抱えている傾向がみられた。
脳梗塞(のうこうそく)や肺がんなどでも同様の傾向だった。糖尿病の場合は、口腔内の菌との関連も指摘されているという。
県歯科医師会情報管理委員会の神田貢委員長(46)は「歯が少ない高齢者は多い人より重い疾患を抱え、入院費や薬代がかさんでいることが裏付けられた。もっと口腔ケアに関心を持ってほしい」と話している。
【神戸新聞】
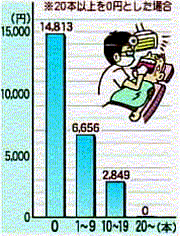
70−89歳の歯の数と1カ月の医療費、月最大1万5000円差
県歯科医師会2万7000人調査
。