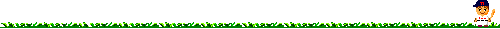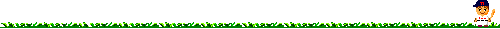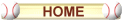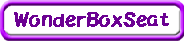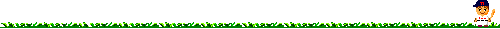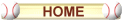
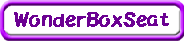
【The Skipper is Oyaji師匠】
たとえば、打撃の技術的傾向で
>3)体が、投手方向に動きながら、当てようとする
>5)ステップしながらスイングする
この二つは結構厄介だと思います。「前に行くな!」「着地してからスイングしろ!」
というアドバイスだけでは修正できません。
①打撃を指導するということは、先ず発見しなければなりません。
②次にそれを今、矯正するべきなのか、それよりも先に矯正するべきところがあるならば
そこだけに取り合えずは絞るべきなのか?
そのことによって、両方が矯正される場合もありますし、
これは今、着手してもこの子の身体のバランスや身体能力から考えると無理だし
逆に長所を摘み取ってしまうかもしれないと判断する場合もあると思います。
③そして矯正するべきだと判断すれば、先ず、「こうしてみよう」と言葉で伝えてみます。
これで直ぐできる場合もありますし、次の練習日までに修正できている子もいますが、
ほとんどそんなケースはありませんね。
一番大事なことは、その子のイメージの中に入り込むことだと思います。
言葉で言うと簡単ですが、実際にはこれは大変なことです。
しかしこれしか方法は有りません。
稀に本人の「気付き」によって達成できることもありますが、これは
偶然の産物でこれにいつも頼っていたのでは、指導者ではなく評論家になってしまいます。
①発見(診断)②判断(治療法の確定)③指導、矯正(治療)
①、②、③のプロセスを踏んで、子供達の指導にあたることを考えればこれは全く、
お医者さんと同じではないかなと思うんですよ。
Ryanさんが時々掲示板などでボヤいていますが、①の発見だけの第三者が周りに一杯居る訳です。
「ドア―スイングになっている」「アッパーになっている」「開いている」等など・・・。
所謂、評論家です。
「そんなもん初めて見た時からわかっとるわい!」と言いたいですよね。
そんな奴に限って実際指導すると「あ、こいつはセンスが無い。」ということで終わってしまうんです。
「発見だけだったら、賭け屋のおっちゃんでもできる」です。
じゃあ、「イメージの中に入り込む」とはどういうことなのか、
上の二つの場合を私なりの「入り込み方」で述べてみたいと思います。
>3)体が、投手方向に動きながら、当てようとする
>5)ステップしながらスイングする
反動を利用して体をぶつけるように打つとボールを飛ばせるという錯覚のイメージを持っているのです。
これは漠然としたイメージからきているのですが、
例えばドッジボールのような野球のボールよりも大きくて重いものをバットで打とうとすれば
バットの重さを利用するのでは無理があります。
そこで遠心力を捨てて、反動を利用してバットを壁のように使って体をぶつけていくのです。
そんな子はバットを振るのではなく、当てにいくような形になります。
相手のスピードを利用するようなイメージでしょうか?
遅いボールは遅くバットを振るし、速いボールは(速くではなく)慌てて振るという合わせにいく動作になります。
つまり遠心力を全く期待していないのですから、当然そうなるのです。
このイメージがその子の中に本能的にあるということを、指導する側がしっかり押さえておかないと
「何でできない」「何で判らない」こんなストレスばかりが溜まることになります。
この子のそういった潜在的に持っているイメージをさてどうやって取り除いてあげるか、
ここが指導者の腕の見せ所だと思います。
まるで新興宗教に取り憑かれた信者の
マインドコントロールを解くような根気のいる大変な作業になる場合が多いですね。
子供によって多少言い方やドリルの使い方が変わる場合がありますが、私の経験から言うと、
大体は次のような方法になると思います。
1、ノーステップで打たせて見る。
2、体重移動を全くしない。(最初から最後まで後ろ足体重)
3、素振りの時、後股関節の上に頭があることを確認させる。
4、ヘルメットのマークの所をノックバットで押さえて、ノックバットが動かないように素振りをさせる。
(右打者ならば、左打席側に指導者が立って)
5、ロングティーで指導者が同じ位置に立って頭を手で押さえておく。
6、丸椅子に座らせておいてロングティー。
1から6まですべて身体からバットが離れていく感じを掴ませる目的です。
副作用として下半身が回らない、後ろ足がベタ足になるとか、前脇が空く、
極端なアッパーになるなどの問題が出たりしますが、これは初めから承知の上です。
初めは真中、真中低め、内側低めこのへんの球をヒットできるようになるはずです。
この辺で、今まではバットの芯で打っても周りが「ナイスバッティング!」と声を掛けてくれても
本人は「今ひとつ納得できない」状態なはずだったものが、
自分の身体の力で飛ばしている実感を感じているはずです。
このへんの気持ちの変化なども指導者は見逃してはいけないと思います。
この確率が高くなってきてから、次に下半身の使い方を指導します。
病気を治す時、一旦熱が出たりなどの副作用が出るのは仕方の無い場合があります。
指導者側がある子供に対して、手術を決定したならば何の為に手術をするのかということを
先ず本人にしっかり伝える方が良いと思います。
仮にその時点で本人は何の事を言っているのか理解できないとしてもそうした方が良いと思います。
何故なら、子供も成長していますから、その途中で理解できる可能性も有る訳ですからね。
この子は説明しても判らないだろうから、
取り合えず俺の言う通りにしとけばいいんだという指導者は信用できないですね。
与えた一つのテーマから発展して、その子なりの「気付き」や本人にしか判らない「発見」が
あるかもしれないということは指導者側も期待していいのだと思います。
さて、期間をどれくらいにしたらいいのかということですが、私も一概には言えません。
その子が持っているイメージのすべてを洗脳しようとする場合もあるでしょうし、
部分的なイメージの修正ということもあるでしょうからね。
私の場合は、「この夏までは・・・」とか「この冬の間に」とか「6年生になるまでは」
とかいう言い方が多いですね。
ポイントは決してこれが君の最終的な打撃スタイルではないということを知らせておくのが大切だと思います。
お父さんに、今やろうとしていることのテーマや何故そうするのかということの意味を説明しておく
のもいいかもしれませんね。但しそれはそのお父さんをよく知った上でのことですが。
少年野球の掲示板に度々出てくる勘違いおじさんなんかだと、困ります。
技術的なことじゃなくてメンタル部分で協力してもらえると助かります。
大きな手術ではあっても部分的にはある程度結果を直ぐ出して上げないといけません。
そうでないと子供はめげてしまいますからね。少しの結果が出て「よっし!」と
そこでまた子供なりの勘違いが起きてしまって、何時の間にかもとに戻ってしまうと
いうこともよくあるので気をつける必要があります。
つまり手術のあとのリハビリ期間は充分に取らなければならないということです。
一時的によくなって安心して、不養生しているとまた直ぐもとのイメージが復活して
くることがよくありますので、そうなるとまたゼロからということになりますので結
果がでても少しの間は次のステップに進むのは慎重に考えた方が良いと思います。
動作はできても、イメージが追い付いてこないということはよくありますからね。
看護士の役割をお父さんやコーチにお願いしておくのがいいかもしれません。
ここまでは「大きな手術」について話しましたが、本人、指導者、そしてできればもう一人、
この三者が一つの大きな覚悟をもって取り組むくらいがいいでしょう。
少しオーバーなくらいが子供に理解させるには丁度だと思います。
右打者を左に転向させるのも「大きな手術」のうちに入ります。
実はこの冬の間に左に転向させる子が一人と、まだ今年ヒットを打ったことの無い子
のイメージ修正という大手術が控えていて今、手術の計画書を作成中です。
指導者は、しっかりとした手術の計画書を作成することも大事ですね。
次に、ちょっとしたイメージの修正の場合ですが、
これは本人の自覚が芽生えればそんなに時間はかからないです。
こんな場合私はよく器具を使います。
前足爪先を開かない、ステップ幅を狭くするなどは器具を渡して
「これ使う?じゃあ貸しとくから出来るようになったら、返してくれ。」決して「これを使え!」では駄目です。
本人の自覚を促す訳ですから、「あ、これを使えば早く矯正できるはずだ」と思わせることが大事です。
大体は2,3週間で「ありがとうございました。」と返しにきます。
(現在、一ヶ月経つのに戻ってきていない奴がいるのを思いだしました。こういうのは大体やってないはずです。)
「小さな手術」は病気でいうと盲腸みたいなもので、
いづれは直るのですが薬で治療するか手術で早く直すかの違いだけだと思います。
もうひとつ、子供とイメージを共有するというか「俺はこう思っているんだが君はどう思う?」
ということを伝える為に言葉ではなく「逆療法」というのがあります。
ただこれは、即治療になることもありますがあくまでも「気付き」を促すことを目的としています。
例えば、アウトステップを修正したい場合にはホームベースから離れて立たせます。
するとバットが届かないので、踏み込むようになります。
普通は気持ちが逃げていると考えて近づける人が多いようですが逆の方がいいですね。
それとか、先にありました「ステップとスイングが同時」も
オーバーにこれを先ずやらせてみるのです。
足を大きく上げてタイミングを取らせます(王選手のように)。
そしてその足が下りてくるのと一緒にスイングさせます。
これを何度か繰り返して、次にその足がおりてきた時にバットが
構えた位置から動いていない状態を作らせます。
それから、スイングの始動でグリップが一旦下がる子なんかはグリップを上げて構えさせるのでは無く、
逆に極端に下げた状態で構えるとそこに意識が行きやすくなります。
本人は足を上げて打っているつもりはないのですが、打つ前にどうしても上がってしまい
目がぶれたりその分タイミングが遅れてしまう子なんかは、逆に早い目に意識して
大きく足を上げてタイミングを取るように言ってみて下さい。
そして一定期間をおいてから「足を上げずに打ってみなさい。」というとできます。
いくつもありますが、矯正したい個所を矯正しようと必死になる前に
本人に指導者が矯正したい個所を強く意識させることがいい結果を生むことが多いです。