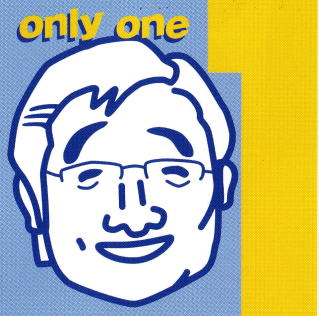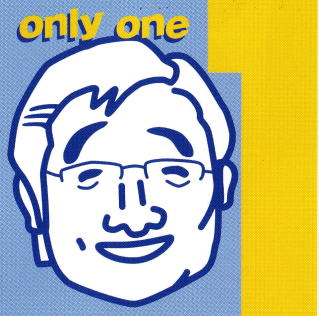二酸化炭素(CO2)など地球全体の気温を上げる[温暖化問題]を話し合う国際的な枠組みが“決裂寸前”となっている。ブッシュ米新政権が3月末、先進国による温暖化ガスの排出削減目標を決めた97年12月の京都議定書に「不支持」を打ち出したためだ。
京都議定書は、2008〜’12年の間に90年時の排出量から先進国全体で5.2%減らすことに合意したもので、アメリカの削減目標は7%だが、CO2排出は今も増え続けており、90年比では35%も減らさなければならないという。これは一つの家庭で考えれば、電気・ガスを3割以上節約する生活へ切り替えることと同じだ。
アメリカがこの条約を保護にした背景には、過度の制限を嫌う産業界の強い反発がある。温暖化ガス全体の1/4を出す「世界一の排出大国」の一方的離脱に、欧州連合(EU)各国や環境団体などから「許されない暴挙」と避難が集中。7月にドイツ・ボンで再会される京都議定書参加国の話し合いは、いったん仕切り直しとなる。
しかし、これらの削減目標を達成しても温暖化の進行は妨げない。ではどうしたら良いか? アメリカは自動車、工場、家庭、その他の排ガス防止への技術改革はもちろんのこと、植林や熱帯雨林保護によるCO2吸収を削減量に含める案を主張した。
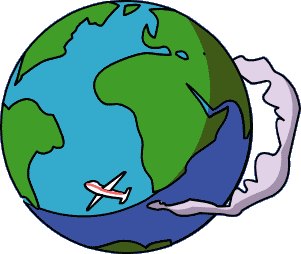
現在、排出されているCO2の25%は、かつて植林された森林が吸収していることを考えれば、積極的に検討するべきである。経済を優先すべきか? 環境を優先すべきか?という論議では解決しない問題である。京都会議後にもそのことを裏付ける科学的な論拠が発表されている。
’00/5月、各国の専門家が参加した、最も権威ある国連「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)が特別報告で、植林や森林の回復が進んだ場合、森林によるCO2吸収量が京都議定書で決めた削減量を上回る試算を出している。
要するに、緑化運動に各国が積極的に取り組めば、温暖化問題はクリア出来るわけで、各国の事情やメンツを重んじて、安易な二者択一的選択をすれば、益々環境は悪くなる一方である。
経済を軽視して環境を考えても良い結果を得ることは出来ない。日本のバブル経済期には、民間企業の多くが「砂漠緑化プロジェクト」「バイオ・テクノロジー」等の研究所を持ち、環境問題に役立つ研究を行っていたが、バブル崩壊と同時に殆どの研究所は閉鎖に追い込まれてしまった。
このように「経済と環境」は切っても切れない関係で、どちらかを選択するという問題ではない。世界を見ても経済が悪化している国々は、環境のことを考える余裕はない。しかも生活の為に、燃料として木を切り、燃やしてしまって、環境を破壊し、気象異変を起こし、作物の不作に繋がり、経済悪化へとスパイラルに悪循環を起こしていくのである。
経済の安定こそが、環境を守るための絶対条件なのである。CO2排出量に伴った植林、森林保全を進めてゆくことで、経済安定と環境保護の両立が可能となるのです。
自然を犠牲にして、経済成長を望むことは大変愚かなことです。しかし、環境保護のために、経済を破滅させることも愚かなことなのです。世界で起きている紛争、戦争の多くは経済悪化が原因です。
経済の成長の否定でも環境破壊でもない、成長と環境が両立するプラス発想こそが必要だと思います。
|
|