| 1 歳神棚 2000,1 神酒口 火焔 故 山梨 清太郎 氏作 澤野 隆 家(清水市) |
| 年中行事・民俗行事と みきのくち1 |
| みきのくちは、現在は、元日を中心とする大正月(おおしょうがつ)に、神棚や床の間、仕事場などに、商売繁盛、豊作、大漁、家内安全など福運を願って飾られることが多いのですが、昔は、ひな祭り、七夕、お月見、恵比寿講、節分、結婚式、地鎮祭、上棟式、祝典、祭典など、お神酒をお供えする場合には一般的に使われて来ました。住宅環境が変わり、神棚や床の間のない家も増えた昨今では、インテリアを兼ねる家庭が増えて来ました。タンスやサイドボードなどの家具の上に置いた徳利、花瓶、ローソク立て、クリスタルなどに挿して、生け花、水引、ピックその他の縁起物の小物と組み合わせて飾るのもよろしいでしょう。 |
| 1 歳神棚(としがみだな) |
| 1 歳神棚 2000,1 神酒口 火焔 故 山梨 清太郎 氏作 澤野 隆 家(清水市) |
| 正月は、一年の幸せをもたらすお正月様という神様を迎えるお祭りです。 歳神(としがみ)棚は、お正月様(歳神様)を迎えるために、臨時に設ける神棚で、その年の恵方(平成15年は、丙「ひのえ」の方角)に向けます。お正月の行事は、一年の実りと福をもたらす歳神様をもてなすものが主でした。 日本では、先祖は死後50年の年忌法要後、神様(祖霊神)という大きな集合神になり、大晦日の夜に、歳神様として天空より下りて来て、元日に、歳や福を与えて下さると考えていました。大晦日の夜、お寿司や大福などのごちそうをご先祖様に供え、下げたものを食べるのも、歳神様をお迎えして歳をとるのを祝う年越しの祝いです。 |
| 渓斎英泉筆 寛政2(1790)〜嘉永元年(1848) |
歳神棚のミキノクチ |
| 辻家勤仕録 |
| 旧幕府旗本の士・辻久五郎は、戸塚備前守支配小普請組(註。禄高3000石未満の無役の旗本・御家人)にして、文政天保年間(1818〜1843)、(江戸)本所亀沢町二つ目に、四百坪余の拝領屋敷に住み、禄高七百五十石余を給わり、知行所相模国高座郡・大住郡・下総国千葉郡の内ニ箇所を有したる人なり。勤仕録と題したる虫食いの一冊の文書は、其の家来・中尾膳衛門が、当時自ら勤仕の顛末を掌記したる書なり。今読史家の参考に供せむ為、原文挿図まで写してここに掲ぐ。 |
| 1−2 歳神棚 |
| 年カミサマ御棚 | みきのくち |
| 御しめ縄長さ六尺。 御台所の隅にて、明きの方(あきのかた・恵方)を後ろにして釣る。御棚仕法は、割り真木(まき)を縄にて編み、竹二本渡し、それへ縄にて釣るなり。供物は、御酒、御据り(鏡餅)、灯明、長御福包ノシ、御福包コンブ、橙、海老、炭、根松、ヤブカウジ、右御幣は、室明院之を献し、巻藁へ立て、荒神様へ上置。元日に至りて流す。棚は、正月十五日御粥を備え、後取之。 |
|
| 風俗画報第262号。明治36年(1903)刊 | |
| 1−3 乾(いぬい)の御祭 |
| 豆腐拍子木ニ切、井カタニクム。 香炉 線香 |
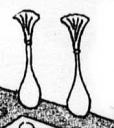 |
|
| 神酒5勺。七色菓子(7種類の粗菓)。五文備(供え)ニ据。御豆腐ニ丁。二股大根。白米一合。黒豆。但、切り火にて善衛門(が)焚き、一升枡へ入れ、備ふ。 右、御押入上の棚へ飾り候事。 |
||
| 風俗画報第267号。明治36年(1903)刊 | ||
| 陰陽道では、東北の方角を鬼門と言い忌み嫌うのに対して、西北の方角(乾の隅)を福門と言い、福神の訪れる所とされます。乾の隅に、蔵を建てたり、福神を目線より高い所に祭ると、縁起がいいと言います。乾祭りは、、馴染みのないお祭りですが、御宮が三つあり、二股大根、黒豆、七色菓子、豆腐などの大黒天のお供物があります。 | ||