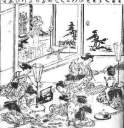 |
 |
女庭訓御所文庫(★) 明和4年(1767)刊 天保6年(1835)再版 |
庚申待ちの図 |
みきのくち(折紙) |
| 年中行事とみきのくち2 |
| 5 庚申待(こうしんまち) |
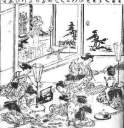 |
 |
女庭訓御所文庫(★) 明和4年(1767)刊 天保6年(1835)再版 |
庚申待ちの図 |
みきのくち(折紙) |
| 庚申信仰は、大坂の四天王寺庚申堂が始まりとされ、江戸時代初期から庚申講が盛んになりました。庚申講は民間信仰で、庚申の日の夜、本尊に無病息災、厄払いなどを願い、その後、食事、飲酒などをして、初期は徹夜、その後は一番鶏が鳴くまで眠らないで夜を明かしました。 江戸時代、60日に一度の庚申講を年6回で3年連続して18回実施した記念に建立されたのが庚申塔(庚申塚)で、今も、村の出入り口や辻などに残っています。 |
| 本図の場合、本尊は、青面金剛(しょうめんこんごう)で、「(かのえさるの日)、男女最愛を致せば、二人ながら大毒にて、年を重ねて病者になる。もし、その夜、子種が定まったなら、その子は、一生病者か、盗人か、大悪人である。よくよく、お慎み有るべく、云々」とあります。 |
婦人が、キセルでタバコを吸ったり、盤すごろくやかるたをして遊んでいます。タバコは、戦国時代に日本に伝わり、江戸時代、刻みタバコをキセルで吸うことが、老若男女を問わず流行しました。 |
| 青面金剛 庚申待ち(庚申講)本尊 |
| 庚申講の仏教系の本尊・青面金剛です。 古代インドでは、仏教はヒンズー教と勢力争いをしていました。しかし、仏教には、仏敵から仏教を守る強力な仏がいないために、ライバルのヒンズー教の最高神の一人であるシヴァ神を、仏法守護の神(マハーカーラ)として取り込み、日本には、大自在天として伝来しました。 さて、掛軸を見ますと、日輪、月輪、青面金剛、2人の童子、4人の薬叉(やしゃ・鬼神)、三匹の猿、番いの鶏が描かれています。青面金剛は、身体の色は青(ものすごく怒っている状態)、目は血のように赤い三眼、頭髪は逆立ち、恐ろしい形相です。手は6本あり、左手の1本では、半裸の女人(ショケラ)の髪の毛をつかんでぶら下げ、2人の邪鬼を踏みつけています。また、頭には髑髏の飾りをし、蛇がとぐろを巻いていて、手足にも蛇が巻き付いていますが、髑髏や蛇は、勇敢さ、力強さの象徴です。 ショケラとは、仏敵シヴァ神の御妃ウマーで、勇猛果敢な女神です。また、青面金剛が踏みつけている邪鬼は、シヴァ神夫妻ともいわれています。ヒンズー教から取り入れた護法神(マハーカーラ)と関連のある青面金剛が、先祖を屈服させているという不思議な構図になっています。薬叉は、虎の皮の裙(スカート)の上に褌をしています。「時を作る」鶏や「見ざる、聞かざる、言わざる」の三猿もいます。 |