| ドライブレポート |
|---|
| 1994年8月 国道152号線〜257号線 踏破 |
| 1994年8月21日 | 静岡県浜松市 → 長野県上伊那郡長谷村 |
|---|
|
●自宅前 午前9時。仮住居の前に自動車を停め、着替え・毛布・懐中電灯・地図・ビデオカメラなどの荷物を積み込む。目覚時計も忘れない。更地になった自宅跡で、出発の光景を撮影する。 | |
|
●浜松市北島町交差点 国道152号線の“終点”。天竜川を東から越えてきた国道1号線が、ここで南下し浜松バイパスへと続く。いよいよここから、長野県上田市を目指しての旅が始まった。しかし、ルートはほぼ決定していたが到着日時は未定。今日の宿泊地もわからない。 | |
|
●鹿島橋 浜松市の中心部を抜ける国道は、ほとんどが4車線以上と整備されている。浜北市の郊外を抜けるところでは、周りに田畑が拡がり長閑な雰囲気が漂う。午前11時、天竜川にかかる鹿島橋に到着、すでに天竜市になっている。天竜川に沿って北上していくにつれ、沿道の景色は急変しカーブ区間も多くなる。 | |
|
●国鉄佐久間線 かつて、天竜市と佐久間町とを結ぶ路線として工事が進められたが、完成直前の橋やトンネルを残し途中で計画は打ち切られた。船明ダムを過ぎた辺り、天竜川の中に寂しく取り残された橋脚が、その名残である。 | |
|
●秋葉ダム 天竜川の河口から2つ目、龍山村に秋葉ダムはある。ここまでは同級生のジモティーも、よくドライブに来るらしい。これからの山道に備えて、暫し休憩を取る。 |  |
|
●青崩峠 静岡県磐田郡水窪町。だいぶ山間部に入りラジオの電波も届きにくい。国道152号線はこの先、長野県との県境部分が未開通となっている青崩峠を越えていくが、車は通れない。 | |
|
●草木トンネル 東名高速・第二東名の浜名湖付近と中央高速の飯田とを結ぶ、三遠南信自動車道の計画がある。すでに一部では工事が始まっており、水窪町内にはいずれはこの三遠南信自動車道として供用される草木トンネルが、つい先日開通している。現在は無料開放されているこのトンネルを通り、ひとつ東側の兵越林道を越えていく。 |
 |
|
●兵越峠 静岡県と長野県との県境の兵越峠に到着。ひとっ子一人いない山道を連想していたが、峠の茶屋ではおでんやラーメンが味わえ、運がいいとプチトマトのサービスもある。無茶な峠越えといったイメージはなく、家族連れやシルバーズたちにも行き合う。曇っているからだろうか少し肌寒く、大きな案内板の気温表示計は8月というのに17.2 ℃を示していた。 |
 |
|
●南信濃村〜上村 長野県下伊那郡南信濃村。ただ国道だけが南北に延びる。ここから上村にかけて、ところどころにはきちっと整備された区間が現れる。従来国道152号線は、その上村より未開通部分を経て飯田市へと続いていた。 | |
|
●蛇洞林道 延長された国道152号線は、上村と北に隣接する大鹿村との境界である地蔵峠付近が再び未開通区間であり、蛇洞林道を経由しなければならない。三遠南信自動車道の矢筈トンネルをやり過ごすと、国道通行不能の標識があり蛇洞林道へと入っていく。ここはよく通行止になるところで、この翌日も時間通行止の表示があった。途中までは、近くのしらびそ高原に続くルートがあるせいかしばしば対向車があったが、高原への分岐点が過ぎると林道はダートになる。右側に迫る山の腹を縫うように走り、左側はガケだろうか斜面になっている。雨が降り続き、薄暗くなってきた。ザーザーのラジオには雷鳴だけが響く。山腹から林道に流れ下る雨水と混じって、土砂が崩れている。やっと、大鹿村の標識を見つけると、再び国道152号線に合流できる。振返りざま、地蔵峠を戻る国道のルートを探すと、木々で覆われたオリエンテーリングコースのような獣道が、峠への道標の先に続いていた。 | |
|
●翌朝から通行止 午後4時半。車中泊を覚悟していたので、とりあえず夕食を仕入れる。大鹿村の商店に寄るが、コンビニに慣れているためか少し品薄な感じがする。チョコレートとビスケットが、夕食となった。少し行ったところでふと工事予告を見ると、翌朝からしばらくの間、この先の峠が通行止になるという。薄暗くなる中、急遽もう一つ峠を越えることになる。 |
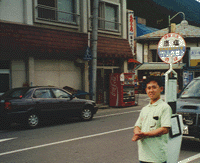 (写真は翌年の再訪時) |
|
●霧の中 延々と山の谷間を、1.5車線の国道152号線は続く。国道番号を示した道路標識が妙に新しく、周りの風景とのギャップが可笑しい。小雨が降る中走り続けるが、集落はなくやがて長谷村との境の分杭峠に着いても、碑が建っているだけで茶屋もない。ただ、峠の北側が開けており天候次第ではいい景色が望めるかもしれない。霧の中を1〜2km走った中沢峠で、駒ヶ根市へと続く県道が分岐。霧が濃くなり、前照灯を遠方に切り換えて進む。 |
 |
|
●美和郵便局 天竜川の支流、三峰川の畔まで来ると集落に出逢う。美和湖畔で公園の案内を見つけ停車、もう周りは闇に包まれている。美和郵便局の近くの駐車場で、今夜は休むことにした。 | |
| 1994年8月22日 | 長野県上伊那郡長谷村 → 長野県松本市 |
|---|
|
●目醒 午前5時。周囲がだんだんと明るくなり、自然に目醒める。新聞配達のおっちゃんが不怪訝そうにこちらを見て行く。浜松や京都では真夏日・熱帯夜が続いているはずだが、高原の朝は涼しい。毛布があってよかった。 | |
|
●長谷村〜高遠町 田舎の朝は早く、車は速い。峠を越えた向こうの街に通勤するのだろうか、午前6時だというのにジモティーの車はみるみるうちにバックミラーに迫ってくる。ウインカーを左に出しブレーキペダルを2回踏むと、猛スピードで追い越され視界から消えていった。 | |
|
●コシンニャ 山林の中、勾配がきつくなった杖突街道を抜けていくと、視界が開ける杖突峠に着く。北西に位置する諏訪湖は霧に霞んで見えない。午前7時、ちょうど茶屋が営業を始めた。朝御飯にタイミングよく、数人のトラックドライバーに続いて店に入る。ブラジルの味が楽しめる店で、コシンニャというブラジル風コロッケを注文。旅の記念にスタンプを記す。 |
 |
|
●諏訪湖 杖突峠の北側は、ヘアピンカーブが連続する。対向車に注意して峠を下り、中央高速が見えるともう茅野市街である。時間に余裕があるので諏訪湖に立ち寄ることにし、渋滞する国道20号線を避けて県道岡谷茅野線にルートを取る。右手の視界が開け、眩いばかりの水面が拡がるとそこは諏訪湖。釜口橋で天竜川を渡り、天竜公園を訪れる。標高759mの諏訪湖より200km彼方の遠州灘にむけ、天竜川は今日も流れている。 |
 |
|
●白樺湖 諏訪湖をあとにし、上諏訪郵便局で局印を押してもらう。茅野市から再び国道152号線を白樺湖方面に進むと、レジャー目的の他府県ナンバーの車や観光バスが急増し、すれ違うライダーも目立つ。市街地のような雰囲気が漂うと、そこはもう白樺湖。長野県屈指の観光地、家族連れやカップルがい〜っぱい。行き交う人々がこちらに向ける視線が妙に冷たく、決して一人で訪れてはいけないと痛感した。 | |
|
●姫木平〜丸子町 大門峠を下ると、国道152号線は上田市までほぼ平坦地を走る。姫木平付近で、また雨足が強くなる。ペンション『森の音楽家』はすぐ近くだが、若旦那の“りょうちゃん”が農村への出稼ぎで留守のため、無念ながら通過した。きれいに整備された国道152号線を進んでいくと、沿道に設けられた駐車スペースには、トラックが休んでいる。郊外型の大型店も見られ、上田市も近い。 | |
|
●上田市大屋交差点 午後1時、千曲川を渡り国道152号線はいよいよ上田市に入った。大屋駅近くで信越本線を跨ぎ、国道18号線に合流。一日半をかけ、やっと“起点”の街に辿り着いた。感動のレポートを撮り、上田市の中心部である上田駅前へ向かう。 | |
|
●青木峠 今夜の宿は松本市内のYHである。松本市へと続く国道143号線を選び、青木峠を越えていくこととする。対向しやすい区間であるが途中から急勾配が続き、ところどころには拡張工事がなされている。峠付近の会吉トンネルは手掘りで、信号機による片側交互通行である。 | |
|
●松本市 午後3時、浅間温泉YHに到着。ここでは食事提供をしていないが、近所の大衆食堂を案内してくれる。近くに温泉の銭湯があるらしいが、地図に迷って辿り着けなかったのが残念だった。また夕方少し市内に出て、あがたの森公園に立ち寄った。 | |
| つづく |