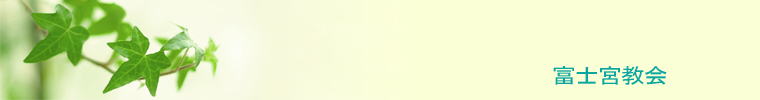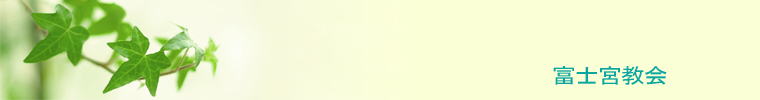|
|
| 礼拝説教(3月 28日) |
マルコ福音書14章32〜42節
「十字架への道」
今日から受難週に入ります。イエス様と弟子たちは最期の過越の食事をされた後、ゲッセマネの園に行かれます。そこは祈りの場所でした。イエスは弟子たちに、「わたしが祈っている間、ここに座っていなさい」と言われます。さらに、ペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人を選び、園の奥にすすまれます。
そして彼らに「ここを離れず、目を覚ましていなさい」と言われます。。彼らに忠告した後、ひどく恐れてもだえ始め「わたしは死ぬばかりに悲しい」とご自身の胸のうちを話されます。
35節では地面にひれ伏し、父なる神に「できることなら、この苦しみの時が自分から過ぎ去るように」と祈られます。
ルカ福音書の同じ箇所では、イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。
“汗が血の滴るように地面に落ちた”のでした。(ルカ 22:44 )
イエスがもだえ始められたのはなぜでしょうか。人間イエスが十字架の外面的な苦悩のほかに、精神的な苦悩が伴っていることが考えられます。精神的な重圧は「汗が血の滴るよう」なほどに苦痛を伴うのでしょう。
これは当事者でなければわからない“いたみ”です。また一方では
36節の前半では「アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯をわたしから取りのけてください」と嘆願されます。しかし、何でもおできになる父なる神様はイエスのこの苦悩に対して特別反応しておられません。
十字架を避けることが父なる神の御旨であればイエスの十字架は起きなかったことでしょう。
しかし、イエスの十字架は神様の御旨でもあったと言うことになります。
「この杯」とは目の前に迫る十字架をさしていますが、人間イエス、としては十字架は避けたい、それがいつわらざる本心かも知れません。
しかし、神の子イエス(当を得ているかどうか?)が後段において「しかし、わたしが願うことではなく、御心に適うことが行われますように」と祈られるのです。
泉田昭先生はイエス様のこの後段の祈りを「祈りの真髄」といわれます。
37,38節、ここでイエスが弟子たちの中から3人を選ばれた理由がわかります。
イエスはこの3人に「目を覚まして祈って」欲しかったのです。
それからイエスは「戻って御覧になると、弟子たちは眠っていたので、シモン、眠っているのか。わずか一時も目を覚ましていられなかったのか。
誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えても、肉体は弱い」と言われます。。
ペトロたち3人を眠りに誘うものがあって、
彼らは“目を覚まして祈っておれないほど”の誘惑を受けていたのです。
このようなことはわたしたちの日常でも体験しますから、単なる睡眠不足か霊的誘惑か見分けられるとよいと思います。
41 節イエスは三度目に戻って来て「あなたがたはまだ眠っている。休んでいる。もうこれでいい。
時が来た。人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て、行こう。見よ、わたしを裏切る者が来た。」
といわれます。
イエスの十字架は、人間の罪を帳消しとするためにはどうしても必要でした。
お祈りします。
|

|
|
|
|