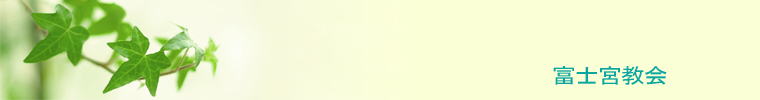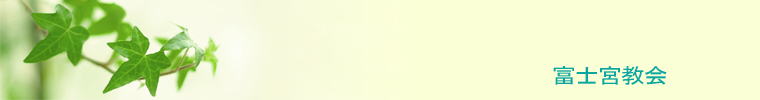|
|
| 礼拝説教(7月 11日) |
2010年7月11日 聖日礼拝 説教要旨『何でもはっきり見えます』
聖書:説教テキスト マルコによる福音書8章22〜26節
イエスの一行はベトサイダという村に着きました。人々はそこに一人の盲人を連れてきました。
この目の見えない人をいやしてほしい、と。イエスはその人を村の外に連れ出されます。
そしてその目に唾をつけ、両手をその人の上に置いて、とありますが、岩隈直先生は「両手を彼の目に当てて」と
よりわかりやすい訳をしておられます。
イエスは盲人の手を取って、「何か見えるか」とお尋ねになります。
24節で、すると盲人は見えるようになって(アナブレボーということばは「見上げる」という意味にも使われます)
「人が見えます。木のようですが、歩いているのが分かります」とこたえます。それはぼんやりと見えたのでしょう。
25節「そこで、イエスはもう一度両手をその目に当てられると、
すると、よく見えてきて何でもはっきり見えるようになった」とあります。
この25節は新改訳では「それから、イエスはもう一度彼の両目に両手を当てられた。
彼が見つめていると、すっかり直り、すべてのものがはっきり見えるようになった」とあります。
彼の目が見えてくるのがわかるような感じがしますが、彼が見つめている(エネグレペン)は
目を開いて見つめる、神経を集中して注視する、という意味があります。
彼はイエスの言われることに神経を集中して応じたのでしょう。
26 節の最後の部分でイエスは、「この村に入ってはいけない」と言って、その人を家に帰されました。
この人ははじめから終わりまでベトサイダという村には入らなかったことになります。何か意味があるのかもしれません。
わたしは今のところその深い意味は見いだせませんが。
福音書にはわたしの知るかぎりでは目の見えない人をイエスがいやされた話は3つです。
3者を比べてみますと共通点もあり、独自のものもあります。
A:ベトサイダの盲人のいやし、(マルコによる福音書8章22〜26節)、
B:盲人バルテマイのいやし、(マルコによる福音書10章46〜52節マタイ、ルカにも並行記事あり)
C:生まれつき目の見えない人のいやし、(ヨハネによる福音書9章1節〜)
共通点;イエスをとおして見えなかった目がみえるようになった。
異質点;A:他の人々が連れてきてその人の目にイエスが手を当てて(2回)いやされた。
B:イエスが通られるのを聞いて、本人がイエスに懇願する。
C:生まれつき目が見えないのはこの人の上に神の御業があらわれるためといい、唾と土でどろを作り、
彼の目に塗り、池に行って洗いなさい、と指示される。
これらの盲人のいやしから、神様はことをなすとき、「画一的になさらない」ことがわかります。
また、みんな目が見えるようになったように、神様はわたしたちを本当に愛し、憐れもうとされていることです。
あなたの願いはききとどけられていますか?ベトサイダの盲人が神経を集中して主イエスの手を見つめていた
ように、神様をじ〜と見つめてみましょう。
ガラテヤ書5章1〜12節
『キリスト者の自由』
キリストはご自分の体をもってわたしたちを罪から自由にしてくださいました。
律法の支配下にあったイスラエルの民を律法から自由にしてくださいました。
なのにガラテヤにあるキリスト者の群れはユダヤ主義者たちによって律法の奴隷としてつながれようとしているです。
ガラテヤ教会の人々を惑わそうとしている人々はキリストの救いの恵みがわからない人たちでした。
そこで、「わたしパウロはあなたがたに断言します、
もし割礼を受けるなら、あなたがたにとってキリストは何の役にも立たない方になります」と強い語調で
ユダヤ教の生活に戻ることはキリストの恵を失うと警告します。
割礼とはイスラエルの男性に定められた宗教的儀式ですが、広くは「神の律法を守ることによって救いにあずかる」生き方をいうのです。
パウロにとってイエス・キリストによる救いはなににも代えがたい救いでした。
彼はローマのキリスト教信徒たちにキリストの救いにあずかる前の自分を正直に告白します。
「わたしは、自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、
かえって憎んでいることをするからです。わたしはなんと惨めな人間なのでしょう。
死に定められたこの体から、だれがわたしを救ってくれるでしょうか」(ローマ 書7章15 〜24節)と。
律法にしばれらた惨めな自分から救ってくださったのはイエス・キリストでした。
イエス・キリスト以外に救いはないことを彼はよく知っていたのです。
イエスは山上の垂訓の中で言われました。
「わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。
廃止するためではなく、完成するためである」(マタイ5章17 節)と。
人々が律法を守り通して行けないから、
イエスは救いを完成するために十字架の上で血を流してくださいました。
したがって、神様はイエス・キリストを信じる者には律法を完全に守れなくても生きる道を開いてくださったのです。
パウロは「割礼を受ける人すべてに、もう一度はっきり言います。
そういう人は律法全体を行う義務があるのです」(ガラテヤ5:3)というのです。
さらにパウロは「キリスト・イエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です」と愛の実践を強調します。
1517年マルチン・ルターはドイツの宗教改革に着手しました。
長年培われてきた生活習慣は簡単には修正できませんが、ルターは信仰に立って聖書にもどるようすすめました。
彼の努力と愛の実践によって今日のプロテスタント教会があるのですが、
イエス・キリストを信じる信仰に立って、真理に向かう愛の実践が「キリスト者の自由」を生むということができます。
お祈りします。
|

|
|
|
|