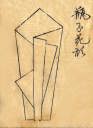 |
|
| 瓶子に挿す蝶花形です。 左右の区別はありません。 |
|
小笠原流諸礼折形(★) 享和元年(1801)刊 菊池 貞蔵 著 |
小笠原流の、礼法と折形を説明した本です |
| 折形本体伝之叙(はしがき) 「夫(それ=そもそも)折形は、木火土金水の五行より生じて五色の性を有す。」 |
折形、水引は、陰陽道と関連があります。 折形は、御幣などと同じく、折る手順、折り線や面の数、角や辺が、神仏や陰陽五行を象徴しているようですが、秘伝とされています。 |
| みきのくち 6 |
| 9 瓶子花形(へいしはながた) |
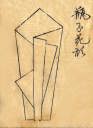 |
|
| 瓶子に挿す蝶花形です。 左右の区別はありません。 |
|
小笠原流諸礼折形(★) 享和元年(1801)刊 菊池 貞蔵 著 |
小笠原流の、礼法と折形を説明した本です |
| 折形本体伝之叙(はしがき) 「夫(それ=そもそも)折形は、木火土金水の五行より生じて五色の性を有す。」 |
折形、水引は、陰陽道と関連があります。 折形は、御幣などと同じく、折る手順、折り線や面の数、角や辺が、神仏や陰陽五行を象徴しているようですが、秘伝とされています。 |
| 9−2 神酒口(みきのくち) |
| 神酒口・右です。左は逆に折ります。 | |
| 夫 礼方諸流ありといへども 小笠原吉良の二流は天下に行われ 諸礼の書物など先板に出せるといへども 其書の中に 折形はあらましにして 安く(たやすく)これなく 此冊は 小笠原流の縁者の人に求めて 折形の図の (以下略) 君子の便里にそなへしむ |
| 10 神酒口(みきのくち) |
| 女子教科 包結之栞★ 斎藤 円子 編 明治33年(1900)刊 |
|
| 神酒口左 ・神酒口右 | 小笠原流包結のしらべ(昭和6年刊)掲載の、「婚礼式場神酒口(みきぐち)」と同一です。 |
|
|
|
| 10−2 神酒口 |
 |
 |
|
| 長さ5寸(全長7寸6分) |
瓶子飾雌蝶 水引結、足等を足す |
瓶子飾雄蝶 |
| 雌蝶・雄蝶 | 礼式折紙水引結 | |
| 小林 きよ 氏蔵 |
西田虎一著 昭和12年3月発行 |
|
| 明治43年静岡県安倍郡有度村に生まれて育った本多 きよ氏が、大正末期の尋常高等小学校時代、手工科の授業で習った折紙(折形)の教材の一つです。裏に、「有度尋常高等小学校」という朱印が押してあります。形は、神仏具店市販の神酒口1の305番と同じ雄蝶雌蝶で、庶民の婚礼の際、御神酒錫(お神酒徳利)に挿して飾る草のランクの神酒口です。なお、尋常小学校は6年、尋常高等小学校は2年が修業年数でした。 |