外構工事
メッシュフェンスの憂鬱
☆11月26日
玄関前ステップの作成が始まりました。

玄関ポーチの手前に半円状のアプローチが設けられます。洗い出し仕上げでアクセントがつけられる予定です。
GLが12cm高くなった影響で、ここは階段のようなステップになります。


レンガを縦に立てて半円状のアーチを形作っていますが、レンガ同士の隙間にモルタルを流して接着されているのは、まだ一部だけです。

玄関ポーチの横にはPF管(?)が引き出されています。表札付門灯(ファンクションポール)の電源線を通すためですね。

建物西側に土が足されました。これで、ようやく基礎フーチングも完全に隠れました。
他の三面と同じように、このあと防草シートが敷かれて砕石が撒かれて完成となるのでしょう。
フェンス関連の作業も継続しておこなわれています。


化粧ブロックの上面にコンクリートが流されてフェンスの支柱が固定されました。あとはメッシュのフェンスが貼り付けられるだけです。

西側の隣家との境には、2mくらいの高さのコンクリートブロックが立てられています。しかし、道路に面した部分は、1mほど塀が途切れている(道路の見通しが悪いため、かつて隣家にお願いして一部撤去してもらった。)ため我が家で低いフェンスを立てることにしました。その基礎が作られました。

建物の東側に赤土が少し搬入されました。左の写真のような赤土の山が三箇所作られていました。
外構の設計図に三本の木が植栽されたイメージが描かれていたのですが、その三箇所だけに赤土が入れられるとは想像もしていませんでした。
少しずつガーデニングを進めていくつもりだったので、全面に近いくらい赤土を入れてくれるだろうと当然のように思っていました。
外構の打ち合わせは決して細かくやってなかったので、意思の疎通は不十分ですね。

東側駐車場と西側駐車場ともにコンクリート仕上げになります。
そこに敷かれるワイヤーメッシュが準備されていました。150mmピッチのφ3.2mmのワイヤーメッシュでした。建物の鉄筋に比べると針金にしか見えません。
二回目のワックス塗りが本日おこなわれました。玄関に注意書きが貼られていました。
展示会を実施する直前に一回目がおこなわれたのですが、通常二回やってくれるものなのでしょうか?それとも特別大サービスなのでしょうか?不明です。
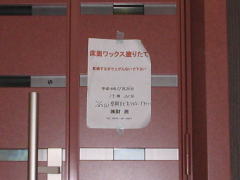
☆11月27日
複数の作業が並行しておこなわれています。まずは西側駐車場の作業です。


建物北側のコンクリートブロックにはメッシュフェンスが設置されました。また、西側隣家との境のフェンス用のコンクリートブロックが施工されました。
フェンスはメッシュ形状のものを選択しました。個人的にメッシュフェンスに高級感を感じないため、大嫌いでした。高級感を追求するなら鋳物フェンスなどが良いのですが、我が家のフェンスは総延長26mに達するため鋳物フェンスで揃えたら、結構な金額になってしまいます。そこでアルミのパイプが組み合わされたようなフェンスで妥協するつもりでした。しかし、業者さんに聞いたところアルミパイプの組み合わされたようなフェンスは強度が低く、プランターなどを掛けると変形する場合があるそうです。強度を求めるのならメッシュのフェンスですと言われました。(鉄の表面にコーティングして防錆対策をしたもの)
県道沿いの建物とフェンスの間に植栽ができればプランターをフェンスに掛けるようなことは考えないのですが、基礎のコンクリートと汚水管・雨水管が地中にあるため一切の植栽が出来ません。したがって、殺風景を隠すにはプランターをフェンスに掛けることになるだろうという結論に至ったため、仕方なくメッシュタイプのフェンスを選びました。後悔が無いと言えば嘘になるけど...。

玄関前のアプローチのステップは、全てのレンガがモルタルで固定されました。
欠けそうな感じを受けるのですが、経年変化は大丈夫なのでしょうか?それとも月日を経て風化していく感じも良しと考えるべきなのでしょうか?

玄関の横に門灯のファンクションポールが設置されました。コンクリートが固まるまではつっかい棒で支えるようです。
東側駐車場はコンクリートを流す準備がされています。


転圧されて平らに均されたところにメッシュ状の鉄筋が敷かれています。(一部敷かれていない部分がありますが...。) 鉄筋は砕石の上に直に置かれているだけなので、建物の鉄筋とは異なって、”かぶり厚”は考慮されないんですね。
コンクリートの割れを防止するための伸縮目地の部分は木材が置かれています。(写真左)
写真右は車止めのコンクリート丸柱の部分です。丸柱の養生は取り去られていました。


水道メーターのボックスと汚水枡は、保護フィルムが貼られていました。
休日の土曜日だったので施主工事を一つ実施しました。

玄関に取り付けるはずだったスポットライトを有効利用するために、人感センサーと併せて冷蔵庫の壁に自分で設置しました。